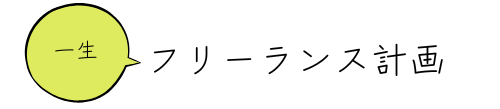・AI資格って結局どれがいい?
・文系や未経験でも合格できる?
・フリーランスに本当に役立つの?
AIが話題になっている今、何か始めたい気持ちがあるものの、どの資格が自分に合っているのか分からず、手が止まっている人はいないでしょうか。
実は筆者も文系出身で、現在は広報ライターとして働くかたわら、AIツールを活用しています。
そこで「AIの知識をもっと深めたい!」と考え、2025年5月にG検定を独学で受験し、無事合格しました。
この記事では、同じようにフリーランスとして働きながら「AIを学びたいけど迷っている」という方に向けて、初心者にも挑戦しやすいAI資格を5つ紹介します。
AI資格には「知識系」と「実技系」がある
AI資格は、大きく2つのタイプに分けられます。それが「知識系」と「実技系」の資格です。
知識系のAI資格は、AIや機械学習、データ分析の基礎知識、活用事例、法律・倫理などを身につけることが目的です。問題は主に選択式で、プログラミングのスキルは必要ありません。
一方で、実技系のAI資格は、実際にAIモデルを作ったり、プログラムを書いたりする力を評価するものです。実務経験や、Pythonなどのコーディングスキルが求められる場合もあります。
「どちらがいいか分からない」と迷う方はまず知識系の資格で基礎を固めてから、実技系にチャレンジするのがおすすめです。
フリーランスにおすすめの知識系資格
AI初心者や文系出身の方におすすめなのが、まず「知識系」のAI資格です。プログラミング不要で、AIの仕組みや活用法を基礎から学べるものが多く、フリーランスでも独学で挑戦しやすいのが特徴です。
生成AIパスポート
生成AIパスポート(SHIFT AI)
主催:生成AI活用普及協会(GUGA)
内容:生成AIの基礎知識、活用方法、著作権や権利侵害のリスクなど
特徴:生成AIを安心・安全に活用するための「常識」を身につけることが目的
受験費用:11,000円
予想勉強時間:約30時間
合格率:75~77%前後
G検定(ジェネラリスト検定)
G検定(ジェネラリスト検定)
主催:日本ディープラーニング協会(JDLA)
内容:AI・機械学習・ディープラーニング・活用事例・法律や倫理など幅広く網羅
特徴:ディープラーニングを含むAI技術の基礎知識と、ビジネス活用のための応用力を評価することが目的
受験費用:13,200円
予想勉強時間:50~100時間
合格率:65%~75%
DS検定
DS検定(データサイエンティスト検定)
主催:一般社団法人データサイエンティスト協会
内容:データサイエンス、データエンジニアリング、ビジネス力、統計学・数学、データリテラシー、活用事例など
特徴:データサイエンティストの登竜門的な資格、データ分析やAI活用の基礎力を証明するのに最適
受験費用:10,000円
予想勉強時間:150~200時間
合格率:約50%前後
3つの中で特にハードルが低く「まずはやってみたい」人におすすめなのが生成AIパスポートです。必要な勉強時間も30時間程度で難易度は「かなり易しめ」と評価されているので「まずは基礎から」と考える方にぴったりの内容です。
「もう少し本格的に学びたい」という方は、筆者も合格したG検定がおすすめです。合格率はおおむね65~75%と高水準。出題範囲は幅広いですが、しっかり学べば初心者でも十分に合格を目指せます。
一方、DS検定は合格率が約50%前後で、データサイエンス・エンジニアリング・ビジネスの3分野にまたがる内容が特徴です。実務に直結する力を身につけられるため、キャリアアップを見据える方は視野にいれておきましょう!
フリーランスにおすすめの実技系資格
・AIを実際に使いこなしたい
・知識だけでなく手を動かしたい」
そんな方におすすめなのが実技系のAI資格です。プログラミングや実装スキルが必要になるため、少しハードルは上がりますが学びが実務に直結します。ここでは長期的にAI分野で活躍したいフリーランスに向けて、2つの代表的な実技資格を紹介します。
E資格
E資格(エンジニア資格)
主催:日本ディープラーニング協会(JDLA)
内容:応用数学、機械学習、深層学習、開発・運用環境の4分野から出題。ディープラーニングの理論やアルゴリズム、実装、画像認識・自然言語処理など
特徴:AIエンジニア向け。受験にはJDLA認定プログラム修了が必要。理論と実装をバランスよく学べる
受験費用:33,000円
予想勉強時間:100~300時間
合格率:約60~65%
受験条件:JDLA認定プログラムの修了が必要
E資格は、ディープラーニングに関する理論・実装・応用力をバランスよく身につけられる、AIエンジニアを目指す人の登竜門といえる資格です。
受験には指定講座の受講が必要ですが、その分「基礎から順を追って」学べる構成になっており、初心者にも理解できるように設計されています(実際に文系出身やPython未経験の方も、約半年の学習で合格を果たした例があるよう)
AI実装検定
AI実装検定
主催:AIEO AI実装検定実行委員会
内容:B級~S級まで段階別にAIの実装力を評価
特徴:PythonでAIを動かす力が身につく実践向け資格
受験費用:B級9,900円~S級33,000円
予想勉強時間:30~200時間
合格率:約50~70%(級により異なる)
AI実装検定は実務でAIを「使う」スキルを身につけたい人向きです。B級(初級)は「実際にコードを書く力」が問われ、Pythonによる簡単な実装スキルをWeb環境で試す内容になっています。
フリーランスがAI資格を取るメリットとは?
フリーランスがAI資格を取ることにはメリットがあります。資格はゴールではなく、仕事に活かしてこそ価値が出てくるもの。「実際にどう役立つのか?」という視点で、3つの利点をご紹介します。
① スキルや知識の客観的な証明になる
AI資格を持っていることは、「この人はAIに関する知識をきちんと持っている」という信頼につながり、クライアントや企業からの信頼性が高まります。
実際にAIを開発できなくても仕組みや可能性を理解しているだけで「話がわかる人」としてクライアントとの会話がスムーズになります。名刺やプロフィールに記載するだけでも印象が変わることもあるはずです。
② 実際の仕事に活かしやすくなる
例えばライターならAI技術に関する記事の企画や執筆に役立ちます。マーケターならAIツールを活用した分析提案など、業務に直結する場面が増えるなど、仕事に活かせる場面が増えます。
またAIの基礎を知っていることで「新しい分野への挑戦」にもつながります。他業種との協業や、新しいサービスに関わるチャンスが生まれることもあるはずです。
③ キャリアの選択肢が増える
AIの知識は、フリーランスの働き方に「安心感」と「広がり」をもたらします。今は「先の見えない時代」といわれているので、この先どんな社会変化があり、自分がどう動いていくかはそのときになってみないと分かりません。AIに関するスキルを磨いておくことは営業力の強化、スキルアップにもつながり「自分への投資」になると思います。
AI資格取得前に注意すべきこと
AI資格を目指す前に、いくつか確認しておきたい大切なポイントがあります。知らずに始めてしまうと途中で挫折したり、思わぬ出費につながることもあります。以下の3つは特に意識しておきましょう。
① 受験資格や条件の確認を忘れずに
AI資格の中には、誰でも受けられるものと、条件があるものがあります。たとえばE資格の場合は、受験前に「JDLA認定プログラム」の修了が必須です。申し込んだあとで受験資格がなかったと気づかないように、公式サイトで開催時期や要件を必ずチェックしておきましょう。
② 費用と時間のバランスを見極める
資格によって、学習時間や費用の負担は大きく異なります。たとえばG検定は1万円台で受験できますが、勉強時間は50~100時間が目安です。私自身は60~70時間かかりました。
一方、E資格は講座代を含めると10万円以上かかる場合もあります。自分の予算や目指したいレベルに合わせて、無理のない選択をすることが大切です。
③ 独学か講座受講か、自分に合った学び方を選ぶ
資格によっては独学でも合格可能ですが、効率よく学びたい場合や時間が限られている方には、要点を整理した講座の受講もおすすめです。
最近は無料で学べる動画コンテンツや、有料でも短期間で学べる講座も多くなっています。自分のペースや学習スタイルに合う方法を選びましょう。
G検定は独学で合格できるおすすめAI資格
フリーランス初心者が最初に選ぶなら「生成AIパスポート」や「G検定」が個人的にはおすすめです。
私が「生成AIパスポート」ではなく「G検定」を最初のAI資格として取得したのは、1歩進んだ知識を身に付けたかったから。しかし勉強時間を合計してみると70時間ほどは費やしたので、そこは「やるからには勉強が必要」でした(AIの知識がほぼなかったもので)。
ご自身の興味や学習スタイルに合わせて、無理のない資格選びをしてみてくださいね。